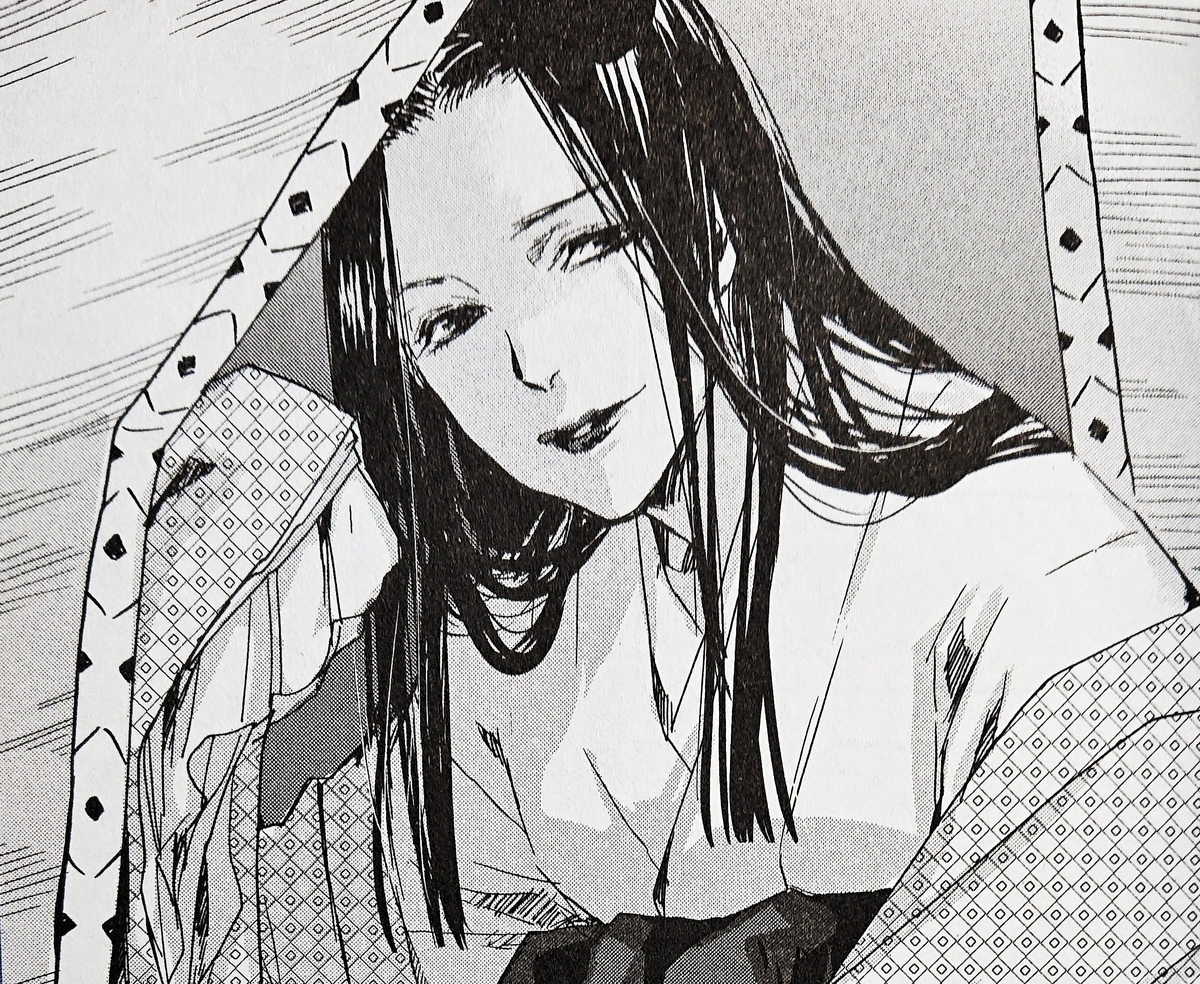平安時代(か明治時代)にタイムスリップしたいなぁと常々思っているAuraです。
そんな僕が愛読しているマンガ、『応天の門』(おうてんのもん) についてご紹介します!
キービジュアル画像です
『応天の門』とは
作者やあらすじなど
灰原薬(はいばらやく)さんが2013年から連載しているマンガで、2021年4月現在、14巻まで発売されています。
灰原さんの他の作品には、オリジナル作品『回游の森』やコミカライズ作品『されど罪人は竜と踊る』(原作:浅井ラボ)などがあります。
そして『応天の門』のあらましは……
ひきこもり学生の菅原道真と京で噂の艶男・在原業平――身分も生まれも違う、およそ20歳差のふたりが京で起こる怪奇を解決!? 「回游の森」「SP」の気鋭・灰原薬がおくる、平安クライム・サスペンス!
左が在原業平(ありわらのなりひら)、右が菅原道真です。
主人公のひとり、菅原道真は特に有名でしょう。
高官の地位に昇りつめるも大宰府に配流され、その後学問の神様として祀られていることは、歴史の授業で覚えたという方が多いかと思います。
歴史好きの僕としましては、「菅原道真が主人公!?これは読むしかない!!」となりました 笑
そしてもうひとりの主人公、在原業平といえば、高校で習う『伊勢物語』の主人公のモデルとされる人物…!
僕は国語好きでもあるので、「在原業平も主人公……!?これは!読むしか!ない…!!!」と重ねて思った訳です 笑
と言いますのも、平安時代を舞台とする創作物ってあまり思い浮かばないですよね。
マンガにせよ小説にせよ、戦国時代か江戸時代(特に幕末)が多く選ばれています。
僕自身、それらの時代がテーマとなる作品もまた愛好していますが、『応天の門』で、道真と業平がタッグを組んで活躍するという趣向の面白さには目を見張りました。
「探偵もの」であり「歴史もの」
あらましに「平安クライム・サスペンス」と書いてあるように、ジャンルとしては探偵ものになります。
平安時代においては、何か怪異が起こると、鬼や物の怪が原因だと考えられることが多々ありました。しかし道真は「そんなものいるわけがない」と言い放ちます 笑
そして業平とともに、人間が引き起こした事件の真相を解き明かしていく——
というのが『応天の門』の基本的な話のつくりです。舞台が平安時代なので、さすがに現代で見られるような大胆なトリックが使われている訳ではありません。
ただ、逆説的な言い方かもしれませんが、平安時代だからこそのトリックに注目してほしいなぁ~と思います。
さらに広めれば、事件を通じて描かれる平安時代の雰囲気が分かることもこのマンガの魅力でしょう。平安時代って、古典をよく知らないと中々イメージしにくいですからね…。
(まぁ、古典好きがこのマンガを読むんだろうとは思いますが……笑)
写実的な画風もこの魅力を支えています。服飾や建物など、当時のものがしっかり描かれています。
そして、『応天の門』から歴史的事件の方の「応天門の変」を連想された方もおられるでしょう。
この事件の中心人物、伴善男(とものよしお)もマンガに出てきますよ!笑
藤原氏もバンバン登場しますし、『応天の門』には歴史ものとしての一面もあります。
主な登場人物
菅原道真
©灰原薬/新潮社
主人公その一。18歳ごろ。後に学問の神様と言われるだけあって、ずば抜けた頭脳の持ち主。
徹底した合理主義者で、理屈っぽい性格です。そのため、先にも書きましたが、鬼や物の怪の類は全く信じていません。また、他人に毒づいて正論パンチをかますこともしばしば 笑
(優しい一面もあります!)
本人としては屋敷にこもって書物を読んでいたいのですが、業平など周囲の者に相談されたり巻き込まれたりして、事件解決のため動くことになります。
僕は幼いころに歴史マンガで道真を知り、「温和な人」というイメージを持っていたため、『応天の門』でニヒルな造型の人物になっていて驚きました 笑
しかし、怨霊を信じない道真が、死後怨霊として考えられるなんて、なんたる皮肉……。
©灰原薬/新潮社
↑一般的な道真のイメージからはかけ離れた言動をしています 笑
在原業平
©灰原薬/新潮社
主人公その二。30代半ば。検非違使(けびいし)という都の治安を守る役職についています。さらに、和歌の才に秀で歌人としても名を馳せています。
何か事件があると、解決の糸口をつかむため業平が道真に話を持ちかけることが多く、道真に大体嫌そうな顔をされます 笑
時には年若い道真に、年長者として助言を与え導くことも。
そして何より、数多くの女性と浮名を流す色男。そのせいで起こる事件もあるという…笑
しかし、特に藤原高子(ふじわらのたかこ)への想いを胸に秘めています。
©灰原薬/新潮社
↑業平の方は大体イメージ通りの言動をしていますね 笑
紀長谷雄(きのはせお)
©灰原薬/新潮社
道真の友人。創作キャラっぽく見えますけれども、実在の人物です。
上の画像からもなんとなく伝わってきますが、少々情けない性格の人物…笑
学問をおろそかにして遊興に入れ込み、その中で度々トラブルに巻き込まれては、道真にため息をつかれています。
ただ憎めないところもあり、「悪いやつ」ではありません 笑
藤原高子(ふじわらのたかこ)
©灰原薬/新潮社
藤原良房(よしふさ)の姪で、帝に嫁ぐことになっています。21歳ごろ。色気やば
以前、業平と駆け落ち未遂をしました。そして今なお、業平への想いを断ち切れずにいます。
そう、業平と高子といえば『伊勢物語』の「芥川」の段に出てくる男と女のことですよ…!!
昔、男ありけり。
女の、え得まじかりけるを、年を経てよばひわたりけるを、からうじて盗み出でて、いと暗きに来けり。
芥川といふ河を率て行きければ、草の上に置きたりける露を、「かれは何ぞ。」
となむ男に問ひける。(後略)
見覚えありませんか…!?この後、女は鬼に食われてしまいます。(実際は兄たちによって連れ戻されたと「芥川」の後半に書いてあります)
僕はこの「芥川」で『伊勢物語』が好きになったので、『応天の門』で業平と高子の関係がどう描かれていくかには目が離せませんでした 笑
補足になりますが、本来、「高子」は「たかこ」ではなく「たかいこ」と読みます。現代の読者に馴染みやすい読み方にしたのかな…?
藤原基経(ふじわらのもとつね)
©灰原薬/新潮社
高子の兄であり、良房の養子。良房とともに朝廷内で権勢を振るい、藤原北家の繁栄を目指しています。
表面上は、貴族らしく穏やかな立ち居振る舞いをしていますが、冷徹かつ酷薄な性向で、目的を果たすために手段を選びません。
実の妹である高子は、そんな基経を「恐ろしい」と思っています。
上の画像で、基経が言及している「あの男」とは業平のことです。
ちなみに良房はこちらです↓ 悪そうな顔してますね 笑
©灰原薬/新潮社
おわりに
『応天の門』についてご紹介しました!
要点をまとめておきます。
〇平安時代が舞台の珍しい作品
〇菅原道真と在原業平がタッグを組む
〇人の手で引き起こされた事件を解き明かしていく探偵もの
〇藤原氏などの有力貴族も登場し裏で事件に関わっていたりと、歴史ものの要素もある
〇登場人物の中では、特に道真のニヒルな人物造型が強烈で面白い
〇『伊勢物語』でも描かれていた在原業平と藤原高子の関係に注目
〇写実的な描写がキレイで、平安時代の雰囲気が分かる
道真と業平が挑む最初の事件は、都で相次ぐ「女官失踪事件」です。
第一話~第三話で扱われ、この話は全てホームページで試し読みできるようになっていますので、ぜひご覧ください。
関連記事
→1冊で『源氏物語』のストーリーを(大まかに)楽しめるマンガの布教記事です。
→貴族の文化や生活について分かりやすくまとめられた、ライトに読める本の紹介記事です。
『文豪どうかしてる逸話集』が面白い|文豪たちの笑えるエピソード
→夏目漱石や芥川龍之介など、誰もが知る文豪たちの人間味あふれるエピソードがたくさん載っている本の紹介記事です。